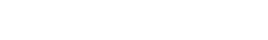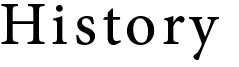平川 敦雄 の歴史 「道のりと思想」
第1章 修業時代 〜東京からフランスへ〜
初心、プロのソムリエを目指して
今から32年前、愛知県から上京したばかりの私は、東京・都心のレストランでアルバイトを始めたのがきっかけでワインの世界に興味を持ちました。小さい頃から自然とのふれあいが大好きでしたので、大学では農学を専攻しましたが、飲食業務はとても魅力的で、レストラン業に自分の専門性を見出そうと考えるようになりました。19歳の時に初めてソムリエの仕事に就いたのち、フランスで一流のソムリエを目指そうと決心しました。リュックサック一つを背に新潟港を出航し、ウラジオストックから鉄道を乗り継いでユーラシア大陸を横断、ロシア、ベラルーシ、ポーランド、ドイツを経由してフランスに入国し、フランス東部のロレーヌ地方で生活を始めたのが1995年夏、22歳の時でした。
アルザスのブドウ園でのテント生活を経て
フランス語を全く知らずに渡航してきた自分を待ち構えていたのは、コミュニケーションができない外国人という厳しい現実でした。1年目はフランスの生活に全く馴染めず、会話能力がないため接客業に携わることはできませんでした。そんな自分にできたのはドイツ、イタリア、東欧をはじめあちこちのブドウ園を野宿で見て歩くことでした。2年目、ブルゴーニュでの収穫後に、アルザスのブドウ園で仕事を始めましたが、部屋代を支払えるお金がなく、畑の脇にテントを構えて生活をしました。焚き火で食事を作り、ろうそくの明かりで勉強をし、温めたお湯をペットボトルに詰め込んで抱きしめて眠る毎日でした。その頃、フランス各地方のワイナリーに100通近い就職願いを出しましたが、ほとんどがお返事すらなく、頂けてもお断りの内容でした。数少ない良いお返事の中に、ポムロールの銘酒シャトー・ラフルールのジャック・ギノドー氏からの手紙があり、その後、研修生として採用されました。ギノドー氏は会話能力が不十分な私に、栽培・醸造技術のあらゆる知識やノウハウを熱心に授けてくれました。そして「頑張れば、フランスでエノローグ(国家醸造士)になれる」と励ましてもくれました。その言葉に刺激され、フランスで認められた醸造家になろうと決心しました。
「人生考え直せ」の言葉に打ちのめされる
ロレーヌ、ブルゴーニュ、アルザス、ボルドーで3年間を費やし、滞在費が尽きた1998年、日本に帰国しました。当初フランスで一流のソムリエになろうとして渡仏したにも関わらず、実現できたのは専らワイン造りの実践だけでした。そして、“ソムリエと醸造家を両立できる人になること” を目標として描くようになりました。1999年に日本の文部科学省認定の技術士(農業)の1次試験を受験して合格しましたが、ある日本のワイン業界の大先輩からの「フランスで働いていたと言ったって、収穫ぐらい誰でもできる。エノローグになろうなんて甘くない。人生考え直せ。」という言葉に打ちのめされ、僅かな手持ち資金で再渡仏に踏切りました。もう日本には戻ってこない覚悟で、日本人に会うことがないラングドック地方の田舎での生活を選択しました。そして南仏のパイオニアワインとして世界的に名高いマス・ドゥ・ドウマス・ガサックのエメ・ギベール氏との出会いがあり、彼の元で栽培者として3年間を過ごしました。人脈の豊富なギベール氏は、私がエノローグになるために常に優しく後押しをしてくれました。
最難関アグロモンペリエに日本人として初めて入学
その推薦先が、マス・ドゥ・ドウマス・ガサックから車で1時間程の距離にあるフランス農水省管轄の国立技術士養成機関、ENSAアグロモンペリエ(現SupAgroモンペリエ)でした。アグロモンペリエはフランスの農学分野で最難関とされるグランゼコールであり、専門課程にブドウ栽培学-ワイン醸造学のコースがあって、その当時は、フランス農水省認定技術士(農学)、醸造士(エノローグ)、ENSA認定マスター・オブ・サイエンス(栽培−醸造学)の3免状を取得できるフランス唯一の教育機関でした。グランゼコールは大学とは別に存在しているフランス独自の教育機関であり、国が優秀な専門的人材を養成する目的で、少人数にて高度な専門教育と研究開発を行っています。ブドウ栽培−ワイン醸造科は44人限定で、私は初めての日本人でした。コート・デュ・ローヌの名門ポール・ジャブレ・エネ社で醸造後、入学許可が得られて厳しい学業生活が始まりました。
学費を稼ぐために箱根で働く
自力で高い学費を支払いながら学業を続けるためには、レストラン業との両立を実現するしかありませんでした。そこで夏の1ヶ月半のみ日本に帰国し、毎年、箱根のホテル(小田急山のホテル、箱根ハイランドホテル)でソムリエとして働きました。そして、飲食業で得た給与の全てをアグロモンペリエの授業料に注ぎ込みました。毎日の睡眠時間が3時間のみで試験勉強の日々、ブドウ栽培学では世界一の研究機関と言われているアグロモンペリエの授業は全てが難題・難問の連続でした。毎週襲ってくる試験では、外国人だからという容赦は一切なく、常に実力を試されました。膨大な参考資料の中から自分流でレジュメをつくり、50回以上読んでから試験に挑みようになりました。このレジュメの多くは今でも私の手元にあり、今でも読み返して暗記を続けています。
念願のエノローグの国家資格を取得
そして約50の試験科目全てに合格し、フランス農水省から2003年、エノローグ国家免状(DNO)を授与されました。31歳の時でした。また厳しい教育の現場で学んだこと以上に、醸造士免状過程の一環としてシャトー・マルゴーの醸造に参加できたことは貴重な経験となりました。更に、技術士免状過程ではボルドー大学醸造研究所にて芳香性化学の世界的権威である富永敬俊先生から、アロマの研究について直接にご指導を授かりました。同級生の多くは世界各地の銘譲ワイナリーの醸造責任者として、また経営者として活躍しています。グランゼコールの専門課程まで辿り着いた友とアグロモンペリエの強力な交流網の中にいることは、今の私の大切な財産となっています。
偉大な富永敬俊先生が目標
がむしゃらに頑張るしかなかった26歳の私に「人生考え直せ」という言葉はあまりにも重たいものでした。日本のワイン業界と一切関わらないという覚悟で向かった南仏での孤独な生活が、やがてアグロモンペリエに進学するきっかけとなり、人生の転機となったことには間違いありません。この言葉がなければ自分の人生は変わらなかったですし、現在の自分には到達していなかったでしょう。今となっては、全く逆の意味で重たい言葉となっています。研究時代にお世話になった富永先生は、私に「サイエンスは思った以上に簡単だ」とおっしゃいました。外国の地で世界的な論文を発表し続けた先生の苦労は計り知れないぐらい大きく、「簡単だ」とおっしゃった偉大な富永先生の背中を今でも目標にしています。科学的知識を最大限に持つことはソムリエとしても、醸造家としても同じことです。実践知識のバックグラウンドの中に理論知識を組み込み、感覚を磨き、感性を高めてゆくことが大切だと思います。
こうして学業と研究生活の修行を経て、毎年夏になると日本でソムリエとして働き、秋からはフランスで醸造家として働くという独自のサイクルが生まれました。そして、醸造家としても、ソムリエとしても高い専門性を持ち、異国の地で生きてゆくにはどうすべきか、そのフィールドを日本とフランス以外の地にも求めてゆくことにしました。
第2章 修業時代 〜南アフリカからブルゴーニュへ〜
エノローグの第一歩、プロヴァンスでのワインつくり
フランス国立の技術士養成機関であるENSAアグロモンペリエ(現SupAgroモンペリエ)にてエノローグ(DNO)と技術士の資格を取得し、ボルドー大学ワイン醸造研究所にて「地中海性気候下の赤ワインに特有な“スパイシーさ”の原因となる芳香成分の特定と畑周囲の植生との関係」という研究テーマを終えた直後の私の目標は、専ら南仏の銘譲ワインの現場で働くことでした。以前、プロヴァンス地方のバンドールにあるシャトー・プラドー1966年と1967年を味わったことがあり、その時の印象がまるでポイヤックの銘酒を味わっているかのような感動で忘れられず、シリル・ポルタリス氏に直接お便りを書きました。そして2003年の収穫期に醸造家として採用されました。樹齢50年〜80年のムールヴェードルを梗ごと仕込み、その後、大きな古樽(フードル)で長期熟成させて出来上がるワインは、フランスで最も熟成能力を有する銘酒のひとつです。30haを有するブドウ園の醸造をほぼひとりで任されることになり、伝統製法を重んじる醸造所で過ごしたこの半年間が、私のエノローグとしての第一歩となりました。
南仏での醸造+歴史に残る猛暑の年
2003年はフランスにおける歴史的な“猛暑の年”で知られています。土壌の水分ストレスが極端に強く、ブドウ樹の成長がストップして本来の糖度が得られていない房や、ブドウ果皮が正常に完熟しないまま干しぶどうになったような状態のものまであり、果実の不均一性を味わいのバランスに変えてゆけるよう、丹念に仕込まねばなりませんでした。最終的には梗からの抽出も程よく、個性的なワインとなりました。これから30年後、31歳の自分が醸造したワインを味わえることを、今から楽しみにしています。
地中海地方の豊かな食材、温暖な気候、美しい街並み、温かい家族のおもてなしに囲まれた南仏プロヴァンスでの生活を思い出すと、そこにはこれまでの私の人生の中で、最もゆっくりとした時間が流れています。そして、その年のワイン醸造が終了後、更なる経験の蓄積を求めて、南アフリカへと出発しました。
南アフリカのワインつくりに飛び込んで
伝統産地から新興産地へー 世界のワイン地図が新しい栽培適地の台頭で大きく変わりつつある今、フランスのような伝統産地のみでの経験ではなく、南半球のワインつくりを通じて専門知識や技術を磨きたいという気持ちがあり、実現に向けて動きました。ちょうどシャトー・マルゴーでの修行時代にご一緒した南アフリカ出身の醸造家からの誘いがあり、2004年の醸造期に、ステレンボッシュのリュステンベルグワイナリーに採用されました。南アフリカは南仏プロヴァンスと同じ地中海性気候を有しており、アフリカ大陸で唯一明確な四季がある国です。リュステンベルグはエステートの設立が1682年という、この地きっての歴史のあるワイナリーで、サイモンスベルグという雄大な姿の山の裾野に美しい畑を有しています。醸造所では自社農園以外のブドウも合わせて約1000トン受け入れていますが、フランスではありえなかった4ヶ月間に亘る長い醸造期間を経験しました。品種としてはシラーやカベルネ・ソーヴィニョン、メルローといったフランス系品種の潜在能力が知られていますが、より標高のある土地での栽培を目指して産地が拡大しており、海由来の爽やかな気候を有している場所では高品質の白ワインも生まれてきています。
時給40円で働く日々、この世の果て
南アフリカではヨーロッパの伝統産地から優秀な技術者が来ていることで産地力向上が目覚ましく、アグロモンペリエ出身のフランス人醸造家も活躍していました。栽培地の拡大を求めて開墾が進められ、醸造所では選果台に20名以上の作業員を配置して完璧な腐敗果除去を行うなど、安くて豊富な労働者の存在が南アフリカ産ワインの品質を確実に押し上げていました。2003年当時、コカコーラ1.5ℓは300円もするのに、黒人従業員の時給が20円、私の時給はその倍の40円でした。そして月400時間という、労働基準が存在しない壮絶な労働環境の中で戦うしかありませんでした。やがて荒涼とした不毛地帯を超えて辿り着くこの世の果ての様な場所で、立ち上がったばかりの新規ワイナリーでの醸造コンサルタント業務の依頼まで来て、毎日朝から深夜まで、休みなしのワイン醸造が続きました。事業開始直後の厳しさを実感すると同時に、文明から離れた極限の地でワインつくりができる喜びを噛み締めて生きました。そうこうしている間に、南アフリカでの滞在資金も尽きました。
再度、夢に向かって
夏の期間は再度、箱根のホテル(小田急山のホテル、箱根ハイランドホテル)に戻ってソムリエ業務を行い、収入を得ましたが、この年、2003年の秋からは、初心である“フランスで一流のソムリエになること”を目指しました。南アフリカの大自然に抱かれたワインつくりからブルゴーニュへの移動は、過去に後戻りしたかのようであり、フランスのワイン文化が有する伝統や歴史の素晴らしさを、これまで以上に重みをもって受け止めました。また同時に、ソムリエという職業はフランスのワイン文化の形成になくてはならないという強い思いを感じました。外国人の私がフランスで認められたソムリエになるためには、知識や技量を保証してくれる免状の取得が必修と考え、フランスソムリエ協会(UDSF)からアドバイスを頂いてCFPPAボーヌのソムリエコースを目指すことになりました。
ブルベ・プロフェショナル・ドゥ・ソムリエを目指して
CFPPAはフランスの国家認定資格であるブルベ・プロフェショナル・ドゥ・ソムリエを1年で取得できるフランス唯一の教育機関であり、当時はソムリエ協会の会長を9年間も努められたジョルジュ・ペルチュイゼ氏が担当教師を務めていました。濃密なカリキュラムで、地理学、栽培学、醸造学、経営学…といった諸々の教科の試験を全てパスしなければならず、外国人にはかなりハードな授業です。アグロモンペリエでエノローグの専門過程を経ていた私は、常に高得点を目指して挑みました。
そして2005年に、首席にて資格取得となりました。ブルゴーニュソムリエ協会認定のソムリエとなり、ジャルダン・デ・センスやランスブールといった、当時ミシュラン3つ星のレストランでソムリエとして働きました。フランスでのソムリエ呼称認定を目指す日本人がもっと出てきてほしいと願っています。
ピュリニー・モンラッシェにて
その頃に出会ったのが、ピュリニー・モンラッシェ村のアンヌ・クロード・ルフレーヴ氏でした。世界のワイン醸造家の多くが、「ピュリニーの様なシャルドネをつくりたい」と言いますが、ドメーヌ・ルフレーヴは、ピュリニーの心臓部に多くの区画を有し、産地個性が非常に明確なワインを生み出しています。アンヌ・クロードは日本人である私に対していつも家族の一員のように接してくれて、2005年から翌年にかけてドメーヌ・ルフレーヴの農場長、醸造長の隣で働きました。今でも共に過ごした時間は人生の宝物です。その後の私の農業への考え方は、この期間に得た思想やインスピレーションによって多大な影響を受けています。そして夜や週末は掛け持ちにてレストランで働きました。フランスでソムリエになることを目指してきてから10年が経ってようやく、フランスで栽培家としても、醸造家としても、ソムリエとしても働くという夢を実現することになりました。
第3章 修業時代 〜ブルゴーニュからボルドー、ロワール、そしてニュージーランドへ〜
10年の歳月を経て、渡仏直後の“何も喋れない。何も出来ない生活”から、私を取り巻く境遇は明らかに変ってゆきました。醸造士、技術士、ソムリエの国家免状を取得し、これらの資格がフランスの名ワイナリーで働くという夢を可能にしてくれました。当時32歳の私はブルゴーニュのドメーヌ・ルフレーヴにて栽培・醸造に携わり、夜や週末はレストランでソムリエとして夢中で働く毎日でした。天候に恵まれた2005年、モンラッシェ、シュヴァリエ、バタール…と醗酵時から畑ごとの味わいの特徴がはっきりと現れ、まさにピュリニーのテロワールが有する物凄さを実感しました。醸造期が過ぎると、冬からは専ら畑作業にて過ごしました。密植で仕立てるコート・ドールでは樹高が低く、屈んで剪定や母枝固定を行わなければなりません。真冬はとにかく厳しい寒さの中での作業の連続でしたが、ルフレーヴが実践するバイオダイナミック農法を通じて各地の農学者や技術者との交流もたくさん生まれ、その農業思想に多大な刺激を受けました。初夏が訪れた頃、アンヌ・クロード・ルフレーヴ氏から、「ここで長く働いてほしい」との嬉しい提案を頂きましたが、更なる経験の蓄積が必要と考え、その時は「はい」とは言えませんでした。「必ず戻ってくる」と伝え、2006年の醸造期からはシャトー・シュヴァル・ブランに行くことを選択しました。全てをやり抜いてからワインを造りたい土地はブルゴーニュであるという気持ちはずっと心の中にありつづけました。
シャトー・シュヴァル・ブランにて
シャトー・シュヴァル・ブランへは、ボルドーの植物生態学・土壌学の権威であるケイス・ヴァン・リューベン氏を通じて採用が決まりました。ケイスは滞在3年目の私を研修生として受け入れてくれたシャトー・ラフルールのオーナー、ジャック・ギノドー氏の大親友で、ボルドーの国立技術士養成校であるENITAの教授を務め、私の母校であるアグロモンペリエでの講義も担当していました。醸造チームの中には、のちにペトリュスの社長となるオリヴィエ・ベロエ氏とも一緒でした。世界を代表する銘酒の中で働いた経験は、今の私にとってかけがえのない財産です。更にシュヴァル・ブラン勤務中に挑戦したのが、ボルドー大学醸造学部が認定するワイン鑑定技能試験“DUAD”でした。醸造責任者、ワインジャーナリスト、ソムリエ等のプロのワイン職人達を対象としており、ドニ・ドゥブルデュー教授やジル・ドゥ・ルベル教授をはじめ、現代醸造学の権威ある先生からフランス最先端のワイン科学を集中的に学ぶことができます。フランス国内で取得できるテイスティングを専門とした資格ではもっとも難しいと言われ、私は2003年にアグロモンペリエで技術士・醸造士の試験をパスした時の過去のレジュメも全て読み返して最終試験に挑みました。最高得点を獲得し、首席にて免状を取得しました。
合格後、研究時代にお世話になったボルドー大学醸造学部の富永敬俊先生を訪ねました。先生は「平川君はいつか必ず日本に帰って日本のワイン業界に貢献できる人になりなさい。それが貴方の使命だ。」と仰いました。それが富永先生からの生前、最後の言葉となりました。
ベルナール・ボドリ氏との出会い
再び夏がきて、例年の様に小田急山のホテル、箱根ハイランドホテルでソムリエとして働き、秋には再度フランスに戻り、ロワール地方シノンにあるドメーヌ・ベルナール・ボドリの醸造者として働きました。前年冬にロワール地方のワイン品評会でベルナール・ボドリ氏と出会ったことがきっかけでしたが、初めてこのワインを味わった時の感動は今でも忘れません。彼のワインはブドウが育った土質ごとに区画個性が明確で、自然に対して誠実、人柄がワインに溢れていました。夏が冷涼であった2007年はブドウの熟度が高くありませんでしたが、醸造期をほぼ任され、満足のゆく高品質のワインを生み出すことができました。シノンでは、ソミュール・シャンピニーやブルグイユの生産者との交流も盛んで、毎日のように飲み会がありました。ロワール地方のワインは美食のテーブルには欠かせない存在です。シノンの品種であるカベルネ・フランからは、熟成するライトボディーからフルボディータイプの赤ワイン、シュナン・ブランからは辛口から甘口、更にスパークリングワインと様々なスタイルが存在し、ロワール産ワインの味わいの多様性はとても奥深い世界です。心の優しいベルナールや息子のマチューのワインには人間味が感じられるという姿を目標に、私自身も、生産者としての思想やこだわりがワインを通じて表現されるように努めてゆきたいです。
ニュージーランドへ
2008年2月にシノンからニュージーランドのマルボロに飛びました。フロムワイナリーのハッチ・カルベレール氏に履歴書と手紙を送ったところ、「これまで働いてきたワイナリーのワインを全て持ってきたら直ぐ採用」との冗談混じりのお返事が来て、即歓迎して頂きました。ニュージーランドは無限の自然の美しさを有しています。温暖な海洋性気候と冷涼な南極由来の南風の影響を受け、また世界で最も紫外線量が多いゾーンにあたり、強い太陽光線を浴びてブドウが育ち、昼夜の温度差が大きい中で熟期を迎えます。「土がまだ若い。」という言葉がありますが、開墾後間もなく、化学肥料等が一切入っていない健全な大地がまだまだ存在しており、生きた土と生態系の存在がワインの品質に作用する自然環境を有しています。5年樹から高品質のワインが生まれている状況は歴史の浅い北海道のワイン産地にも共通する要素があると思います。フロムワイナリーのピノ・ノワールの品質は既に世界的に有名ですが、セントラル・オタゴ、マルボロ、マーティンボロのピノ・ノワールはやがてブルゴーニュに続く産地となってゆくのではないでしょうか。
熟期の見極めと、最低限の醸造的介入
世界中で最も素晴らしいワインは、未熟でも過熟でもなく、正確に熟す品種の存在があって生まれています。地域の生産者と共に、ブドウ栽培の経験的知識の蓄積や歴史づくりへの目標を持ち、その場所と気象の表現を追求してゆかねばなりません。伝統産地のグラン・クリュでは区画固有の味わいが品種個性をも超越しています。ニュージーランド産ワインはブドウ栽培に適する気象面でのメリットが高い産地であることは間違いないですが、若い土壌が有するありのままの精粋さは、ワインに土壌由来の生き生きとした味わいをもたらしています。更にワインの中の精粋さは、我々が味わったり、感じたりすることができるものです。特にワインの味わいの中の余韻は、土壌の状態と土壌微生物の存在の豊かさの表現でもあり、最も素晴らしいテロワールのワインは、生産者の愛情と信頼、そして最低限の醸造介入によって生まれています。
大先輩と過ごした時間を未来に
ニュージーランドの滞在生活を経たために、ブルゴーニュ、採用が決まっていたDRCに行く予定が、フランスの更新ヴィザが発給されないという事態に陥り、ここで私のワインつくりに掛ける夢が一旦終わりを迎えます。アンヌ・クロード・ルフレーヴ氏は毎年のように「一緒にゲーテナムに行こう」と誘ってくれましたが、実現することなく他界されました。私の人生を大きく変えることになったマス・ドゥ・ドウマス・ガサックのエメ・ギベール氏、シャトー・マルゴーでお世話になったポール・ポンタリエ氏、そしてボルドー大学醸造学部の富永敬俊先生…今は亡き大先輩達から学んだ時間や思いを糧に、ソムリエとして日本への完全帰国を決めました。
第4章 夢を求めて 〜フランスから北海道へ〜
フランスからソムリエになるために帰国
フランスでがむしゃらに生きた12年間が過ぎ、2008年、日本に帰国する時が訪れました。テント生活とろうそくの明かりで勉強していた22歳、南仏のブドウ園でヴィニュロンとして働いた26歳、学業と研究に邁進してアグロモンペリエでワイン醸造士の国家資格を取得した31歳、そして更新ヴィザが発給されず、海外でのワインつくりの夢が終わりを迎えた35歳。ソムリエとして完全帰国という大きな転機を迎えた時に、この12年間の修業時代にフランスの銘譲ワイナリーで学んだこと全ては、優秀なソムリエになるための予備知識と考えることにしました。富永先生が生前、私に最後に仰った「いつか必ず日本に帰って日本のワイン業界に貢献できる人になりなさい。それが貴方の使命だ。」という言葉を想い、これまで私が海外生活で生産者として得た経験や言語の知識を活かし、日本のワイン文化の発展のために関わることができる職場を探しました。私は東京でワインに出会い、飲食業からワインの道を志しました。そのために、まずは東京の美食店への就職を考えたのですが、最終的にはずっと憧れであったミシェル・ブラストーヤジャポンで働くことを夢見て、北海道洞爺へ面接に向かいました。ちょうどシェフ・ソムリエを探していたということと、フランスの田舎の様に、地方の豊かな食資源や魅力に恵まれた場所でのやりがいを感じ、北の大地へ渡ることを決心しました。
北海道からライオールへ
ザ・ウィンザーホテル洞爺での就職が決まってから、これまでフランスでお世話になった方々に挨拶に向かいました。売却せずにフランスの倉庫にしまっておいたオンボロの愛車、プジョー205に乗り、ブルゴーニュからライオールを目指しました。晩秋の山道は途中、雪道へと変わり、ノーマルタイヤで中央台地を超えて辿り着いた翌日、ミシェル、セバスチャン、シェフ・ソムリエのセルジオに会うことができました。ライオールのあるオーブラック地方は不思議なことに、大地が空に漂っているかの様に感じる場所です。村の高台にあるレストランの窓から丘陵を見下ろすと、大地に光と陰が交差し、ザ・ウィンザーホテル洞爺からの風景と重なります。周囲を散策すると、玄武岩の岩場から涌き出す水の流れや、荒涼とした大地に牛達の群れが連なって、文明から遮断されたかのような風景の中で素朴な風に触れることができます。自然と、音や色や芳香への感覚が研ぎ澄まされ、ミシェルがライオールの大地から多くのインスピレーションを得ていることを実感しました。
メゾンブラスを象徴する一品である若芽のガルグイユーは、厳しい環境下で生き抜く植物の生命力がテーマとなっています。もともとはハムや野菜を使った地方料理でしたが、幼少の時から影響を受けた母の料理や、オーブラックの花や野菜、ハーブ等の素材、更にミシェル独自の考え方が加わって誕生しました。ソムリエは何よりもお客様にワインや料理をおいしく味わって頂くことが大切ですが、そのためにはその土地を愛し、料理人の思想や歴史を共有してゆくことが重要です。2016年にはミシェル・ブラスが世界のベストシェフのトップにも選ばれましたが、その時、私はライオールの大地を踏みしめながら、世界で唯一の支店を北海道洞爺に出したことへの思いを日本人の立場から共有したいと思いました。
ミシェル・ブラストーヤジャポンのシェフ・ソムリエとして
こうして36歳の私は、第二の故郷フランスで学んだ長い修業時代を経て、ミシェル・ブラストーヤジャポンのシェフ・ソムリエとして勤務することになりました。そのことは、ソムリエとして食と観光の結びつきを追求する立場から、地域農業を守るためにできることはないか、と考えるきっかけとなりました。先輩達が築き上げてきたワインセラーには600種類、12000本のワインが常時保管されています。ワインと料理のマリアージュでは、味覚同士の相性のみならず、ワイン生産者とシェフの各々が求めている要素との相性も目指しました。その上で、シグネチャーデッシュであるガルグイユーと調和できるワインのスタイルは、常にマリアージュの原点として位置づけました。ミシェル・ブラストーヤジャポンのガルグイユーは本店と同じエスプリでありながら、洞爺の自然環境の表現があり、ライオール同様、一皿の上に“光と陰”や“静と動”が表現されています。ミシェル自身が、「洞爺とライオールは瓜二つである」と考えることができる場所が、文化も歴史も全く異なる東洋と西洋の隔たりを超えて存在していることは奇跡的なことだと思いますが、私はフランスでの修業時代同様、美食界にはなくてはならない名店のソムリエとして、北海道の地で働くという至上の喜びを感じました。また、ミシェル・ブラスは家族的なコミュニティを大切にしており、スタッフ間同士でも苗字を使わず、ファーストネームで呼び合います。毎年11月に催されるブラスフェアーでは、本店スタッフが洞爺に来て集いの場が生まれます。現在、日本各地で活躍しているブラス出身者の間でもこのファミリー意識の和をとても大切にしており、この繋がりがもたらす連携と進化は、現在の日本のフレンチガストロノミー界に多大な影響を与えていると感じています。
新たな出会い
フランスから洞爺に来て、更なる出会いがありました。ひとつは発展を続ける道産ワインとの出会いです。そのきっかけとなったのが余市産のケルナーで、コストパフォーマンスと酒質の高さはセンセーショナルな驚きでした。アルザスでソムリエとして働いていた時、リースリングはガストロノミーに何といっても必要不可欠な存在でした。ケルナーにはアルザスのリースリングに共通する要素があり、この品種が存在する限り北海道のワイン産地の将来は明るいと実感しました。このことはのちに、私がケルナーでワインつくりを目指す大きなきっかけとなりました。もうひとつは北海道出身の妻との出会いでした。そしてもう一度、ワイン産地として成立する場で、生産者の一人として挑戦したいと思うようになり、結婚を機にミシェル・ブラストーヤジャポンを退職しました。家庭面では翌年、2012年に元気な双子の男の子が誕生しました。
北海道でのワイン造りに挑戦して
私に北海道の扉を開いてくれたミシェル・ブラストーヤジャポン、余市産ケルナーや妻との出会いを経て、私の心は一旦終わった筈であったワイン造りの現場に戻り、北海道で生産者として挑戦するという道に進むことになりました。その土地から産地固有の味わいを生み出せるかどうかは、つくり出す人の見極め方や考え方次第であり、そこには料理もワイン造りの現場にも共通している要素があると思います。料理界の名店でのソムリエ勤務を経て、寒冷地のブドウ産地から、美食に寄り添えるワイン造りを目指すという目標に辿り着きました。ブラス本店のテーブルに似合うワインの創造を究極の目標として、北海道でしかできない産地個性と風土の表現を追求することにしました。
第5章 夢を求めて 〜余市の風土の中で〜
藤城議さんへのオマージュ
2014年3月、余市町の先進的農業者として65年間励んでこられた藤城議さんの畑を引き継ぎ、株式会社平川ファームを設立しました。余市町は日照時間が長く、北海道の中でも年間を通じて温暖であるため北海道最大の果樹産地が形成されています。平川ファームは積丹半島の付け根部分を流れるヌッチ川が生み出した丘陵に恵まれた南斜面に6haを所有し、日本海を北上する暖流の恩恵を受けた海由来の温暖な気象と、ニセコ方面から吹き付ける山由来の冷涼な気象が交わる場所に立地しています。藤城さんは余市町における桃栽培の先駆者でもあり、91歳で引退するまでリンゴやクルミ、ブドウ栽培も手掛けて、名声を博しました。特にふじ、ハックナイン、昴林、紅玉を主体としたリンゴは大玉でたいへん味がよく、また北海道の気象環境下で適応性の高いツヴァイゲルトや生食用のキャンベルを生み出してきました。平川ファームはこの年、大先輩が残した果樹栽培をそのまま継続し、それぞれ加工による商品化を目指しました。寒冷積雪地である北海道では、積雪による破損や凍害から、ブドウ樹の理想的な樹形を維持することが難しく、樹齢15年を超えると一気に収量が低下して経営が成り立ちにくくなります。欠株の増えた畑の中で生き残っていた古樹ツヴァイゲルトを丹念に栽培し、秋には腐敗果を一粒、一粒をピンセットで取り除いて高品質のブドウを目指しました。翌年、16ヶ月の樽熟成を経て、「藤城議ツヴァイゲルト2014年」が1326本限定で誕生しました。2014年のみの生産ですが、引退後の藤城さんの名を日本ワインの歴史に刻むことができました。
小さな醸造所の設立
農園の中央には、藤城さん自身が手掛けた古い農庫とトラクター用の管理機具庫があり、かつてはその中で果実の選別や出荷作業が行われていました。倉庫の中は、まるで昭和の空気がそのまま取り残されているかのうようであり、ワイン醸造の場所として未来のために残してゆきたいと決心しました。さらにこの場所が神秘的なことは、畑の中心にこの建物が存在し、更に建物の真下、地下43メートルから汲みあがる水が存在し、年間14℃から17℃で、醗酵中のタンクにかけてワインの醗酵温度を調整するには理想的でした。そして2015年2月、株式会社平川ファームが経営主体となり、株式会社平川ワイナリーが設立されました。六次産業化によって付加価値の高い農産物加工品を生み出すことを目標として、ソムリエの方々にも愛される、美食のためのワインづくりを目標としました。2000年以降、純国産100%のブドウからつくられるワイナリーが多く台頭し、日本ワインの世界が大きく変わってゆきました。アジアモンスーンという高温多湿の不利な環境下に負けず、日本人らしい栽培努力によって優れたワインが多く誕生したからです。そして、日本のワイン文化の中心である山梨から、北海道や長野の重要性が増しつつある今、余市は確実に日本を代表するワイン産地へと変わりつつあります。
フルーツワインへの想い
フランスの三ツ星レストランでソムリエとして働いていた時、産地個性のしっかりしたチーズとフルーツワインとの合わせ方に特別な想いを描いていました。ブルーチーズと甘口白ワインとのマッチングはよく知られていますが、チーズにチャツネやジャムの風味を添えるのと同じように、果実味と微炭酸の要素があるシードルやポワレとの相性はたいへん興味深いものです。そこで平川ファーム産のリンゴや洋梨からも、余市の風土の表現を目指したフルーツワインの製造に挑戦することにしました。余市における果樹栽培は、明治5年に北海道開拓使がアメリカ合衆国から果樹類の苗木を輸入したことから始まり、本州に負けない古い歴史があります。リンゴの栽培面積は明治30年に300ha、昭和46年には1080haを誇っていましたが、現在は農家の人手不足や販売価格の下落が加わり、現在はその80%近くが転作や消滅するに至っています。これまでの果樹栽培の収益性が変わり、栽培面積が縮小してゆく一方で、地域のワイン文化の創造や振興のためにできることを、生産者自身が考えてゆかねばなりません。そのためには、その場所でしかできない産業つくりに徹して郷土の味わいの表現に応え、強いブランドを築き上げてゆく必要があります。平川ワイナリーでは瓶内二次醗酵により醗酵由来の炭酸や澱をそのまま閉じ込め、農業の延長上にある素朴な味わいにこだわりました。そして北海道の優秀なチーズや様々な素材、飲食店の料理と組み合わせて相性を確認し、美食に寄り添えるためのスタイルを目指しました。このことは、のちに北海道大学とのコラボレーションでシードルを作ることへと発展しました。
フランスへの想い、フランス系品種の挑戦
余市の畑の中でも特に日照条件の恵まれた平川ファームは、有名な登地区とは余市川を挟んで反対側の沢地区にあり、私がフランスで得てきたことを生かせる素晴らしい自然がありました。標高30m〜40mの穏やかな南斜面に、山々からの強い風を受け、雪の重みで全ての雑草がなぎ倒されることを繰り返し、およそ1400年かかって生まれたと思われる排水性と高い地温効果を持つ真っ黒な腐植土が形成されており、余市を代表する銘譲畑となることを確信しました。藤城さんが残してくれたドイツ系品種の成長や糖度は素晴らしく、また将来的な気象変動の結果を考慮すると、より厳格なフランス系品種に挑戦すべきという思いがありました。そこで主品種であるケルナーに加えて、ソーヴィニョン・ブラン、ゲヴュルツトラミネール、ピノ・ブラン、ピノ・ノワールといった冷涼地に向くフランス系品種の植付けを行いました。気象変動の影響に負けない栽培管理ができるよう、全体の7割を白ブドウの栽培面積に充てました。やがて、試験栽培であったシャルドネにも酒質が見出せたこと、更には、北海道の産地形成に多大な影響を与えたミュラー・トゥルガウの酒質も確認できたことで、挑戦と原点回帰の精神を大切に、品種と自然との調和を目指しました。そして、ブルゴーニュのように、品種の味わいではなく、土地の味わいの創出を追求するため、ラベルには一切、品種名を記載しないこととしました。現在、農地の経営面積は余市の澤エリアのみで20ヘクタールを超え、約7割が栽培区画となりました。
Second Vin ®︎ の誕生
かつてフランスの伝統産地で働いていた時、ファーストワインの醸造はむしろ簡単であり、技術の適用を必要とするセカンドワインをつくることの方が難しいということを何度も実感しました。そこで、グランドキュベに達しないワインを「スゴンヴァン」として、呼称のブランド化を目指しました。世界の銘醸ワインの生産者は、セカンドワインが素晴らしい、という想いを追求したワインで、のちのちに赤、白、ロゼの3色のワインが揃うことになります。北海道の気象環境下では、遅摘みにしたり、たくさん収量を得ようとすると、光合成によって得られた、越冬養分となる炭水化物がブドウ樹体内に不足し、経済寿命が極端に低下します。このため年間を通じた植物栄養と植物生理を考慮した栽培が求められますが、スゴンヴァンとなるブドウは総じて早めに収穫を行い、その後の同じ樹に残された高品質のブドウの遅摘みを可能とするための、醸造技術とブレンド技術に力を込めたワインとなっています。
品種と世代を超えて
世界の産地では、栽培条件の悪い立地から非凡なワインをつくるのは極めて困難である一方、銘譲畑のブドウは醗酵期間中も問題が起こりにくく、ワインの個性が自ずと示されてきます。醸造者による科学的見解の深まりや技術革新は、伝統産地のみならず、世界あちこちで数々の素晴らしいワインを生み出しました。最終的に風土の味わいを表現するということは、伝統産地の生産者が歩んできたように、ひたすら畑のエレメントの追求し、品種の特徴を超越することなのだと思います。世界でその場所でしかできないという畑の個性が根源的な農産物的価値となっており、大地の力の表現であり、農業者の考え方の表現でもあるという姿に理想を抱きます。ワインの本質を追求すると、ローカル思想の創造は重要です。そのためには西欧の伝統産地が実践してきた様に、小規模であっても農業者が六次化したワインづくりであるべきだと思います。北海道の厳しい気候風土からも本場フランスの食卓で楽しんで頂けるワインができると確信しています。アジア北限帯の銘譲ワインを目指すという強い気持ちと共に、平川ワイナリーのワインに、余市の自然を忠実に表現した、農業者の思考を映し出してゆきたいです。
藤城議さんは畑とワイナリーの変遷を見守りながら2016年に他界されました。病院にお見舞いに訪れた私に「どうぞよろしくお願いします。」と深々と頭を下げられたままで扉を閉めたのが最後となりました。北海道の中でも別格と言われる、大先輩が愛した南斜面から世界に誇れるワインを生み出せる様に努めてゆく覚悟です。
考え直すこと、挑戦すること
2016年6月、私は、北海道庁の事業である“北海道ワインアカデミー”の開講式でご登壇頂く先生をお迎えに、受託者代表として余市から新千歳空港へと車を走らせていました。がむしゃらに生きていた当時26歳の私に「人生考え直せ」という言葉を電話越しに発せられた、まさにその先生とお会いする瞬間が訪れたのです。17年という長い歳月を超えて、ワイナリーの経営者として先生にお会いできる運命が巡ってきたことに、特別な想いを感じました。人生には、人を全く違った方向に歩ませてしまうような出会いや言葉があります。まだ若い私にこの言葉への試練はたいへんにつらいもので、日本人と会うことがない南仏の小さな村で3年間、ブドウ栽培家として過ごす道を歩みました。そのことは、その後、フランスの農学部門で最難関と言われるアグロモンペリエに挑戦し、醸造家とソムリエ2つの職業を両立させるという夢へと発展しました。先生との移動時間に蘇る記憶と再生。心の中で、私の人生を大きく変えることになった先生の言葉に感謝をしました。
第6章 日本ワインと料理文化の発展のために
30年の時を経て
1992年、当時19歳の私がソムリエになることを決心してから、四半世紀を超える時間が過ぎました。この30年間、私の夢と希望は常にフランスワインと共にありました。フランスから北海道に舞台が移った今も、優秀なソムリエになりたいと思う気持ちは途切れることはなく、フランスで学んだワインづくりのエスプリは、今後ずっと北海道の地で活かしてゆきます。世界各地では新しい産地が出現し、またアジア圏を取り巻く消費国の状況も大きく変化しました。日本ではブドウ産地の礎が形成されつつある中で、ワインづくりに夢を託したいと考える熱意のある農業者が各地で登場し、日本ワインはものすごい勢いで進化しつつあります。ワイン産業に関わる造り手、事業者、学術関係者、ソムリエ、ワイン愛好家…と我が国のワイン人口は近年、日本の食文化の成熟と共に格段に増加しました。一方で、醸造学上の欠陥を有する酸化的なワインも多く存在し、日本と世界で造り手における知識格差は否めません。日本ワインの今後一層の質的向上と共に、酒質を正しく認識できる有識テイスターやソムリエの役割が益々重要になると思います。
己の顔、己の想い
異文化社会の中で、外国人という境遇に負けずに暮らした苦しさはいつまでも忘れることはありません。専門性を磨くために、現地の言葉を学び、思索を繰り返し、知識の創造に努めた時間は、私にフランスを第二の故郷と言える強い影響を与えました。作業の場では、いわば誰も教えてくれない知識の源が数限りなく存在しています。他人の考え方や職人のノウハウに触れる度に、己の解釈に置き換え、統率し、自己理念の構築のために活かしてゆくことを大切にしました。修業時代に大切なことは、知ることではなく、考えることです。できる限りの思考を持ち、転化することです。そして50歳となった今、ワインづくりを通じて「ワインが私の想いを語ってほしい」と思うようになりました。「水を覗けば己の顔が映るが、ワインを利けば造り手の心が映る。」というフランスの諺があります。ワインはその土地固有の風土の表現であることのみならず、生産者の感性や想いの表現であることは、品質の創造に多元的な大きな意味を含んでいます。自然や思考が映し出されたミシェル・ブラスのガルグイユーのように、独自の精神性を表現し、食に寄り添ってゆけるワインを生み出してゆくことが、私の最終的な目標です。
ローカル思想の創造を求めて
今日、ワイン産地間で生産者の交流が盛んとなり、異文化の伝統産地でワインづくりを学び、そして自国で生かすことができる時代となりました。一方で、新しい土地を舞台にワイン文化を作り上げるためには長い歳月と、本気で銘譲ワインを目指すという意識が必要になってきます。更に家庭の郷土料理の存在が希薄である町では、レストランの場で、ワインと料理との地域的な相乗性が求められてゆかねばなりません。今日、ワインは世界的に見れば生産過剰であり、産地を主張できないワインはやがて消滅してゆきます。そのため、ワインにも食材にもローカル思想の内在が求められてきます。優秀なワインは農業的な特色が強く、画一的な品質を保持できない農産物の特徴を引き継いでいる点、産地名が記されることは、その場所の自然環境と人々の活動に由来する農産物の個性も保証し、地域性や郷土性の継承とも関わっています。かつて私がアルザスのランスブールでソムリエとして働いていた時、地方の食材とワインへのこだわりはものすごいものでした。アクセスが困難な山の中においても、地方を代表する美食レストランと認められると、国境を越えてお客様が訪れます。国際的になればなるほど、ローカルな魅力は強くなります。日本農業に照らし合わせた時、食を通じて田舎の魅力を実感できる場所がもっと必要であり、地方のレストランが果たすべき役割は、今後益々大きくなってゆきます。
かつてのブルゴーニュワインへの想い
フランスをはじめとする伝統産地では、栽培学や醸造学が進んでいるのみならず、味覚学による品質の見極めが、原産地呼称の規程にまで関与しています。16世紀に書かれたブルゴーニュの利酒書 “Gourmet”によると、ブルゴーニュワインに重要な要素として、“コク”、“しなやかさ”、“なめらかさ”、“質感”、“生き生き感”、“ミネラル感”、“香りの余韻”という7点が挙げられており、安定的にこれらの味わい要素を表現できる畑が区別されて、個別に醸造されてきました。以前、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティの地下セラーでロマネ・コンティの1975年を試飲したことがありました。天候条件に恵まれなかった年であり、厚みが全く感じられないワインでしたが、銘譲地独特の香りの高さと、“軽さ”が持つ品質は忘れることができません。また別の機会にヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュの1929年をブラインドテイスティングで味わったことがありました。完全な平衡状態であって、更に驚いたことは、味わいの中にフレッシュ感が持続していることでした。このままずっと、同じバランスで熟成し続けるのではないかと思いました。このようにブルゴーニュでは、伝統産地らしいフィネスがあるワインかどうかが重視されており、タンニンの力強さは追求されていません。過度にタンニンを抽出したワインづくりは、熟成中に乾いてしまうことが度々起こります。品種と土地が最高の組み合わせを実現しているブルゴーニュでは、球体の様にまとまったワインが生み出されており、質感やフレッシュ感、フィネスは、醸造家自らが、醸造過程で引き出してゆかねばならないことです。このようなワインづくりのコンセプトをモデルとして、平川ワイナリーのワインは仕込まれます。
味覚学と美食学の接点を目指して
味の追求は美食学の根幹にあり、美食学は料理とワインを主体とした様々な文化要素で構成されている点、料理人が追求する思想と、ワイン科学になくてはならない哲学との間には多くの共通部分が存在します。その上で、農業者がガストロノミーを意識した栽培を目指した時、ワインは自ずと畑でデザインされてゆくものだと思います。ガストロノミーは、素材が持つ風土の味わい、料理人が奏でる藝、ワインが有する多様な個性等々…との調和を目指すものであり、テロワールが生み出す醍醐味を体感できる瞬間です。ソムリエは、これらがお客様を中心として最高の調和を実現できるよう、その瞬間、その瞬間を見極めてゆかねばなりません。現在、私は美食に寄り添えるワインづくりを目指し、今でも美食レストランのソムリエとしても働いています。それは、ソムリエとしての仕事がワイン作りのためにあり、また農業者として、醸造家としての仕事が好きで、常にプロフェッショナルな精神を大切にしたいです。ワイン文化と美食文化の創造とのあいだで、これからの北海道の産地力を示すための、ひとつの力になれればと思っています。
エピローグ
2022年5月に第2醸造所が完成し、年間5万本のワインを生産。
北海道のみならず、東京やフランスをはじめ、国内外の美食店を中心に販売。